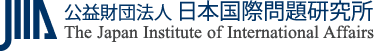ウェビナー要旨
- 日時:2025年3月21日(金)14:00-16:00
- テーマ:核軍縮・不拡散・核セキュリティをめぐる2024年の動向と2025年の課題・提言
- 登壇者(「ひろしまレポート作成事業」研究委員):
戸﨑洋史(広島大学平和センター准教授)
川崎 哲(ピースボート 共同代表)
菊地昌廣(きくりん国際政策技術研究所 代表)
玉井広史(日本核物質管理学会 メンター部会幹事)
西田 充(長崎大学 教授)
樋川和子(長崎大学 教授)
堀部純子(名古屋外国語大学 准教授)
水本和実(広島市立大学 名誉教授)
奥田将洋(国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センターフェロー) - 形式:オンライン(Zoomウェビナー)、日本語のみ、参加無料
『ひろしまレポート』について−『ひろしまレポート-核軍縮・核不拡散・核セキュリティをめぐる動向』は、へいわ創造機構ひろしま(令和2年度までは広島県)「ひろしまレポート作成事業」の成果物として、事業を受託した(公財)日本国際問題研究所 軍縮・科学技術センターにより、平成24年度より取りまとめられてきた。広島県が平成23年に策定した「国際平和拠点ひろしま構想」に基づく事業である。『ひろしまレポート2025年版』は、今春刊行予定。
実施報告
2025年3月21日、へいわ創造機構ひろしま(事務局:広島県)委託「ひろしまレポート作成事業」の一環として、日本国際問題研究所軍縮・科学技術センター(以下、「当センター」)主催の公開ウェビナーがオンラインで開催されました。
ウェビナーでは、まず、戸崎洋史委員(広島大学准教授)がひろしまレポートの概略と、核軍縮を巡る2024年の動向について報告しました。
核軍縮の分野では、核兵器の総数に関する動向、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)へのノーベル平和賞授与、ロシア・中国・北朝鮮による核戦力の近代化と強化の積極性な推進、ロシアによる核恫喝の継続と新戦略兵器削減条約(新START)の履行停止の継続、米国による中露への核軍備管理協議の打診と中露による拒否、拡大核抑止の強化、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)の交渉をめぐる動向、軍縮・不拡散や教育・ジェンダーを含む多様性・包摂性、市民社会の参加の重要性、ならびに核に関する国連総会決議の投票行動について報告しました。
次に、核不拡散を巡る2024年の動向について、奥田将洋(科学技術振興機構)が報告しました。北朝鮮の核・ミサイル開発が継続する中での北朝鮮とロシアの関係強化、イランの核開発やJCPOA再建、保障措置履行の動向、各国での核兵器取得に関連する発言や輸出管理の動向について共有しました。
次に、核セキュリティを巡る2024年の動向について、堀部純子が報告しました。まず、サイバー、ドローン、内部脅威といった近年の核テロの脅威とリスクに加え、)AIの急速な技術進化によりリスクが一層多様化・複雑化している点を説明しました。続いて、核セキュリティ関連条約への加入は漸増しており、条約普遍化の継続的な取組が必要であることを指摘しました。また、高濃縮ウランの最小限化などで取組が進む一方、多国間の取組が停滞している点も指摘しました。
続いて、2025年の核問題に関する課題・提言として、本事業研究委員の川崎哲(ピースボート 共同代表)、菊地昌廣(きくりん国際政策技術研究所 代表)、玉井広史(日本核物質管理学会 メンター部会幹事)、西田 充(長崎大学 教授)、樋川和子(長崎大学 教授)、水本和実(広島市立大学 名誉教授)の各氏が発表しました。
川崎委員は、核兵器禁止条約(TPNW)の現状と課題について述べました。TPNW第三回締約国会議へのオブサーバー参加をめぐって、日本政府とNATO諸国の不参加の決定を説明しました。会議では、核兵器の人道的・環境的影響や、核抑止論のリスクについても批判的に分析されました。さらに、2026年の再検討会議に向けた普遍化の取り組みや核被害者支援の課題が強調されました。
菊地委員は、国際条約における検証制度について述べた。検証制度は軍縮や不拡散のために不可欠であり、INF条約やNPT、CWCなどで確立されてきたことを紹介した。TPNWでは核兵器廃棄を検証するための国際機関の設立が求められているが、その詳細は未確定であり、制度設計や技術整備の議論が必要である。今後、精緻な検証制度が確立され、核廃絶状況が確認できるようになれば、相互信頼が醸成され、核抑止力に依存しない安全保障環境の構築が可能となると期待した。
樋川委員は、核軍縮と公共善 - NPTの意義と効果的な合意形成について述べました。NPTは普遍性を重視し、5つの核兵器国を含む191カ国が参加しているが、CTBTは採択を重視した結果、未発効となっている。FMCTはコンセンサスを重視しているものの、交渉開始に至っておらず、TPNWは発効を優先したが、核兵器国や核保有国、核の傘下にある国々の支持を得られていない。多国間合意を形成するためには、「誰もが最も不満を感じない状態をつくる」ことが重要とされる。「公共善エコノミー」の考え方に基づくシステミック・コンセンサスでは、合意形成の際に抵抗感を基準に判断することで合意を効果的なものにすることが提唱されることを指摘しました。
西田委員は、「トランプショック」と核関連の規範について述べました。トランプ政権の影響により、核不使用・威嚇、核実験禁止、核兵器用核分裂性物質の不生産、核不拡散、核削減の5つの基本的な規範がますます揺らぐ可能性がある。従来の核軍縮・不拡散外交は、日米基軸を中心に同盟国や有志国との連携をベースに、支持を拡大する戦略をとってきた。今後は「テーラード・ディプロマシー(tailored diplomacy)」を採用してはどうか。利益を中心として日米関係を維持しつつも、安全保障・価値外交を基礎として欧州との連携を強化し、グローバルサウスとは戦略的共感を深める形で、より広範な国際的支持を得るべきだろうと提案しました。
玉井委員は、「核セキュリティの強化 - 制度と技術の両輪」について述べました。核セキュリティ上の脅威が深刻化しており、国家が敵対者となるリスクが高まる中、原子力施設への攻撃や脆弱性の露呈が懸念されている。核セキュリティの強化には、条約・法規・国際協力などの「制度」と、物理的防護・サイバー対策などの「技術」の両面からの取り組みが不可欠である。特にドローンやAI、サイバー攻撃、内部脅威の進化に対応するためには、制度と技術を補完し合い、迅速な予測と対応が求められる。国家が脅威となった場合の制度的対応、最新技術の導入、人材育成が重要課題であり、IAEAなど国際社会との協力を深めることが不可欠であることを指摘しました。
最後に、水本委員は「沖縄で考える平和--沖縄県平和祈念資料館のユニークな平和講座」という発表をしました。沖縄県平和祈念資料館は、2019年から「平和への思い」を発信するため、若者を対象にしたユニークな交流プログラムを実施しています。この事業では、沖縄、広島、長崎を含む5か国7地域の学生が集まり、各国・各地域の悲惨な歴史を学び合います。参加者は自分たちの地域の歴史を調べ、プレゼンテーションを行い、沖縄戦を含む様々な悲劇について学びます。このプログラムは、平和の意識を深め、次世代に継承する重要な役割を果たすことを指摘しました。
続いて質疑応答が行われ、FMCTに対してパキスタンの立場や、核軍縮・核不拡散の分野で核大国が国際法の支配を拒否するときにどうやって大国を制御するのか、米・ウクライナの交渉の中でウクライナの原子力施設の所有の課題などについて、活発な議論が交わされました。