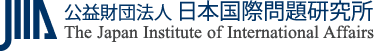「国問研戦略コメント」は、日本国際問題研究所の研究員等が執筆し、国際情勢上重要な案件について、コメントや政策と関連付けた分析をわかりやすくタイムリーに発信することを目的としています。
米国において第2期トランプ政権が始動してから2か月が経過した。新政権が矢継ぎ早に打ち出す政策に、米国内だけでなく多くの国や国際機関にも波紋が広がっている。
関心の集まる貿易戦争の行方は多分に不透明であるが、少なくとも現時点でトランプ政権が課す関税措置の対象は中国のみに限定されておらず、その点で中国は孤立した立場に追いやられてはいない。中国には自国経済への壊滅的な影響を避けつつ、その他の国々との経済関係を強化する余地が残されている状況だ1。
外交面では、米国が戦争の終結に特に注力する一方、中国は和平交渉とは距離を置いている。その傍ら中国は、王毅外相の欧州・米国・アフリカへの外遊2、中国・ハルビンで開催した冬季アジア競技大会を通じた周辺外交の展開、ロシアとの連携確認、イランの核問題に関する中国・ロシア・イランの外務次官級協議の開催、直近では王毅外相の訪日および日中韓外相会談への参加など、米国を意識しつつ広範な外交活動を展開している。
本稿では、2025年の中国外交を分析する足掛かりとして、昨今の中国外交が創出しようとしている国家イメージについて、「安定性」および「確実性」、そして「賦能型大国」という文言に着目して、整理を進める。
世界の安定要素である中国というナラティブ
2025年2月14日、ドイツのミュンヘンで開催されたミュンヘン安全保障会議(MSC)に対面では3年連続の出席となる王毅外相が登壇した。欧州では、トランプ政権主導型の和平交渉や先にMSCに登壇したバンス米副大統領の発言内容などへの懸念が広がっていた。これを受け、2024年に欧州から中国に向けられていた期待(ロシアへのデュアルユース物資の輸出規制やロシアへの影響力行使を通じた和平への貢献など)とは異なる期待が中国に寄せられていた。そうした中、王毅外相はMSCでの演説を通じて中国外交の一貫性や確実性を強調し、「今後も中国は多極システムの中での確実性の要素であり、変革する世界における建設的な力となる」と述べ、米国との違いをアピールした。
また、2025年の中国全国人民代表大会(全人代)3日目の3月7日には、外交部長による恒例の記者会見が開催され、王毅外相が約90分にわたり国内外の記者たちからの23の質問に応じた。そこでも王毅外相は、2024年の中国外交を総括する中で、中国外交が「混迷する世界に貴重な安定性をもたらした」と語った。この発言に対する新華社の記者からの質問に対して、王毅外相はさらに以下のように答えた。
今日の世界は幾重もの混乱の中にあり、確実性はますます世界の希少資源となりつつある。各国、特に大国の選択が時代の方向性を決定し、世界の情勢を左右する。中国外交は、揺るぎなく歴史の正しい側、人類の進歩の側に立ち、中国の確実性で不確実な世界を安定させる3。
中国が世界に対して安定をもたらしているというナラティブは、第2期トランプ政権のもたらしている不確実性や混乱との対比を意図しており、中国外交の様々な場において頻繁に語られるようになっている。全人代での王毅外相の会見内容を受け、3月8日付けの『環球時報』には、「中国外交の『安定性』は世界への贈り物」と題する社説が掲載された。この社説では、多くの人が今回の記者会見のキーワードを「安定性」と「確実性」であると認識していると指摘している。そして、中国外交の安定性や確実性の根源は、混沌とした国際情勢の中でも中国外交が「初心不改」の精神を維持し、人類運命共同体の建設等で着実な進展を積み上げており、将来的にも継続的な漸進的進歩が見通せることにあると論じている4。
新しいキーワードである「賦能型大国」
2024年12月末に習近平国家主席が発した新年祝賀の挨拶では、2024年の中国外交が以下のようにまとめられた。
今日の混迷する世界において、中国は責任ある大国として、グローバル・ガバナンスの変革を積極的に推進し、グローバル・サウスにおける連帯と協力を深化させてきた。 我々は「一帯一路」の質の高い共同建設の深化と着実化を推進し、中国・アフリカ協力フォーラム北京サミットの開催を成功させ、上海協力機構(SCO)、BRICS、アジア太平洋経済協力会議(APEC)、G20などの二国間・多国間の場で中国の主張を全面に打ち出し、世界の平和と安定の維持により積極的なエネルギーを注入してきた5。
中国が世界に対して「積極的なエネルギーを注入」する国であるというのは、自己評価であるとともに、中国が浸透させていきたい国家イメージと言える。このような国家を表した「賦能型大国」という新しい言葉が2025年に入って頻繁に使用されるようになっている。「賦能型大国」の「賦能」は、中国ではもともとはエンパワーメントや権限移譲というマネジメント用語として使用されていたが、近年幅広い文脈で力やエネルギーを与えるという意味で使用される言葉となっている。そして「賦能型大国」とは、Warwick Powellクイーンズランド工科大学客員教授兼太和智库シニアフェローの論考において中国を「enabler」と位置付けた6ことから派生しており、『人民日報』の英訳では「enabler」または「enabling great power」、邦訳では「エンパワーメント型大国」と称されている。「賦能型大国」には、中国の発展(中国式現代化)は世界の発展をもたらすものであり、中国は他国に恩恵や成長をもたらす国であるという意味が含まれている。
上述したMSCでの王毅外相の演説の中でも「賦能型大国」という言葉が紹介されていた。また、『人民日報』では2025年2月17日より「和声」というコラム欄に「断固として『賦能型大国』である」7と題する論評が掲載され、その後8回にわたって同シリーズの論評が掲載された8。上記の一連の論評では、「賦能型大国」という言葉は、中国が人類運命共同体構築という理念を堅持し、国際公共財を提供し、実際の行動をもって世界の平和を維持し、共同発展を促進して大国の役割を果たしていることを鮮明に説明しているし、今後も中国は各方面で「賦能型大国」であり続けると論じられている。また、近代化を達成するために「収奪型」の拡張の道を歩んできた歴史上のいくつかの大国とは異なり、中国は「賦能型大国」であることを決意していると、ここでも対比が示されている。
さらに、2025年2月27日に実施された外交部の定例記者会見において、林剣報道官は中国中央テレビの記者による質問(中国が世界経済の安定剤となることに消極的であるとの海外報道に対する見解を求めた)に応じて、「中国は今後も、発展(開発)を国際的なアジェンダの中心に据え、人類運命共同体という理念を堅持し、断固として『賦能型大国』であり、世界経済の発展にさらなる安定性と確実性を注入する」と述べている9。
今後の世論戦は中国に有利に傾くか
上述の通り、中国の主張は、世界において米国が混乱や不確実性をもたらしているのに対し、中国は安定性や確実性、各国の経済や社会の発展をもたらしているというものだ。さらに、米国が一国主義や保護主義の傾向を強めるのに対し、中国は多国間主義や自由貿易を堅持し、世界平和の建設者、グローバルな発展の貢献者、国際秩序の擁護者であるといった主張も強めている。もっとも、こうした言説をそのまま受け止める向きは、少なくとも欧米主要メディアには見られていない。特に、中国が周辺国に対して行っている威圧的行動に鑑みれば、このようなナラティブは説得力を欠く。
しかしながら、第2期トランプ政権において見られる大統領をはじめとする政権要路の過激な言動や急激な政策転換の作用により、今後中国の主張に説得力を感じるオーディエンスが拡大していく可能性がある。トランプ政権下では米国国際開発庁(USAID)の事業が大幅に削減されることとなり、中国が危険視するメディアであるボイス・オブ・アメリカ(VOA)も機能縮小を命じられ、職員が休職処分状態にある10。中国にとっては、ソフトパワーや自国の主張への支持を拡大させるための機会の窓が開かれていると言ってよい。ただし、自国経済の減速により内需拡大のための財政出動を強める中国が、対外経済協力の規模を大幅に拡大する方向には振り切れないと思われ、上述のナラティブを超えて、中国がそのような機会の窓を活かすためにどこまで尽力する意欲があるのかは疑問である。いずれにせよ、途上国・地域が抱える課題と向き合い、米国が実施してきた支援を自由主義陣営が補完できなければ、中国のナラティブに信憑性を与えることとなろう。
2025年に予定されている主な中国の外交活動としては、5月には対ドイツ戦勝記念式典に合わせて習近平国家主席がロシアを訪問、また近い時期に米中首脳会談が行われる可能性があり、秋には中国が議長国としてSCO首脳会議を中国・天津において主催する。9月の抗日戦争勝利80周年記念行事も2025年の重要な外交行事に挙げられており、中ロの連携を含め、日本としては動向を注視する必要のあるイベントだ。また、2025年下半期には、「北京宣言・行動綱領」採択から30年(北京+30)という節目に、世界女性会議を30年ぶりに主催予定である。米国においてDEI(多様性・公平性・包摂性)が後退し、国際社会による中国の人権問題に対する関心あるいは批判が下火となっている状況下で、中国は国内外で実施している男女平等や女性の活躍に関する成果をアピールすることとなるだろう。このような中国の取り組みや主張が各国にどのように受け止められるかが注目される11。
国際世論が中国にとって有利な状況に発展すれば、中国発のナラティブも国際社会に浸透しやすくなり、また中国による不透明な軍備拡張や力による現状変更、経済的威圧といった行動が問題視されない世論環境が醸成されてしまう危険性もある。世論戦の側面からも、日本にとっては同志国との連携やきめ細やかな対外援助を実施することが今後さらに重要になってくるだろう。
1 次の論考では、米国による関税措置の中国経済への悪影響は大きいが、中国にとってのポジティブな側面として、米国市場の全般的な閉鎖により、グローバル・バリュー・チェーン(GVC)が再編成され、中国とその他の国々との結びつきが強まる可能性があることを指摘している。Christopher A. McNally. "Beijing's Trump Equation." China-US Focus, March 7, 2025. https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/beijings-trump-equation.
2 「中国、米政権との違い強調 25カ国と会談、協調示す 外相外遊終了」朝日新聞、2025年2月27日、第7面。
3 「中共中央政治局委員、外交部長王毅就中国外交政策及対外関係回答中外記者提問」中華人民共和国外交部HP、2025年3月7日<https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202503/t20250307_11570443.shtml>。
4「社評:中国外交的「穏定性」是給世界的礼物」『環球網』2025年3月8日<https://opinion.huanqiu.com/article/4LlmIdpXstT>。
5 「国家主席習近平発表二〇二五年新年賀詞」『新華網』2024年12月31日<http://www.news.cn/politics/leaders/20241231/223dba0aa84840bc8ebf2fdead34df9d/c.html>。
6 Warwick Powell. "Enabler not expropriator." The China Daily, July 18, 2024. https://www.chinadaily.com.cn/a/202407/18/WS66987dbfa31095c51c50eb56.html.
7 英語版のタイトルは「China committed to acting as an 'enabler'」、日本語版のタイトルは「中国は揺るぎなき『エンパワーメント型大国』」。
8 最初の論評とシリーズ全8回の論評をまとめた記事は次の通り。「中国何以成為一個"賦能型大国"」『人民網』2025年3月11日<http://politics.people.com.cn/n1/2025/0311/c1001-40436680.html>。
9 「2025年2月27日外交部発言人林剣主持例行記者会」中華人民共和国外交部HP、2025年2月27日<https://www.fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/202502/t20250227_11565127.shtml>。
10 「米VOAも大統領令でリストラ、権威主義下の国民向け情報発信が機能不全に」『ロイター』2025年3月17日<https://jp.reuters.com/world/us/XACMHEQFWNMSPI566YWGQX6VDA-2025-03-17/>。
11 Phoebe Zhang and Meredith Chen. "As the US backslides, can China claim moral high ground on women's rights?" South China Morning Post, March 14, 2025. https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3302267/us-backslides-can-china-claim-moral-high-ground-womens-rights.