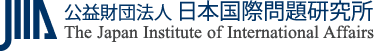本「政策提言」は、3年計画で行われる「朝鮮半島情勢とリスク」研究会の2年目(2024年度)の活動より得られた知見のうち、特に「韓国内政・外交部会」に関するものを総合して作成している。本提言の内容は同研究会が実施した複数の研究会合での所属メンバー間の(「北朝鮮核・ミサイルリスク部会」も含めた)議論に基づいており、また「韓国内政・外交部会」メンバー全員の総意として文章化されている。なお、本研究会の所属メンバーが本補助金事業において披瀝するのはすべて個人的な見解であり、したがって本提言はいかなる組織・機関の見解も代表するものではない。
3年計画で行われる本研究会では事業期間中に、比較的短期のスパンを念頭に置いた提言を継続的に発出して、研究会の成果発表の一部に位置づける方針である。この方針に基づき、本「政策提言」では2024年~2025年にかけての直近の地域・国際情勢を念頭に置きつつ、本研究会(特に「韓国内政・外交部会」)の直接の考察対象である韓国の各分野の情勢についての分析と、それをふまえて日本として考えるべき/取り組むべき課題や、当該分野での対韓政策に関するインプリケーションについての記述をもって、提言のとりまとめを行っている。なお、本提言は直接的には2024年度の動向をもとに作成されたものであるが、特に韓国の政治情勢の動きをふまえつつ、2025年4月初旬に発表したものである点を付記する。
1.総論
2025年4月4日、韓国の憲法裁判所は尹錫悦大統領の罷免を決定した。2024年12月3日の尹大統領による非常戒厳の発令、そして同月14日の国会での尹大統領弾劾訴追案が可決を受けて、韓国では事実上リーダー不在の状況と政治的混乱が続いていたが、6月初めまでに大統領選挙が実施され新政権が発足することになった。尹大統領罷免の時点では、各種世論調査の結果などから与野党政権交代の可能性が高いとされるが結果は予断を許さない。
韓国の弾劾政局による混乱を受けて、尹大統領が主導してきた日韓関係の改善が今後も続くのか、政権交代により日韓関係が再び停滞さらには悪化してしまうのではないか、との懸念がとりわけ日本国内で強くなりつつある。確かに、野党・進歩陣営は尹政権の対日政策を、日本への一方的な譲歩であるとして強く非難してきた。かねてより進歩陣営は、日韓間の歴史問題において日本に厳しい姿勢で臨んできたことも事実である。しかし同時に、昨年末以来、進歩系野党からは日韓関係改善の基調を維持したいとの立場が表明されていることにも留意すべきである。
日本の立場からは、韓国の政権交代如何にかかわらず、韓国との関係が引き続き発展していくよう外交努力を傾ける必要がある。米中対立や露朝関係の深化が続いていることに加え、同盟国である米国トランプ政権の対外政策により国際政治経済秩序が大きく揺らいでいる現在、日韓及び日米韓の協力は日本と韓国の双方にとって不可欠の要請である。
2025年は日韓国交正常化60周年であり、急速に改善した日韓関係が今後とも安定的かつ持続的に発展していく基盤を今一度整える契機とすべき年である。日本としては韓国新政権の発足後、速やかに日韓首脳会談の開催も含めた緊密な意思疎通を図り、日韓の協力を強化できるように努めることが望ましい。
2.韓国の内政状況について
提言
日韓両国を取り巻く国際情勢の厳しさに関する認識の共有をしっかり確認する作業を進めるべきである。特に、韓国の進歩派オピニオンリーダーたちとの認識共有が重要である。
背景
韓国では前倒しの大統領選実施が決まり、次期政権は進歩派となることも考えられる。進歩派政権になったとしても米韓同盟重視の姿勢は堅持されるだろうが、対日姿勢には不透明な部分がある。
想起すべきは尹錫悦政権も単に「対日関係改善」を訴えたわけではなく、厳しさを増す朝鮮半島および国際社会の情勢に対応するためには日米韓連携が必要であり、それをきちんと機能させるために日韓関係の改善が必要だと主張したことである。中国傾斜と言われた朴槿恵政権を考えれば、尹政権の姿勢は保守派だからというだけでは説明できない。むしろ国際情勢への認識が対日姿勢につながりうることを示していると言えるだろう。
ウクライナ戦争が始まったのは文在寅政権末期であり、進歩派の認識も文政権期と同じではありえない。進歩派野党である共に民主党の複数の国会議員は憲法裁判所での弾劾審理が行われていた間に日米両国を非公式に訪問し、政権交代したとしても日米との協力を重視する尹錫悦政権の路線は踏襲すると説明している。彼らはその際、韓国を取り巻く国際情勢が厳しくなっていることを理由として挙げているが、第2次大戦後の国際秩序が根底から揺らいでいるというほどの危機感を抱いているかどうかは、いまだ不透明である。
対韓政策に関するインプリケーション
韓国の進歩派オピニオンリーダー、なかんずく外交政策に関するアドバイザーとなりうる人々と対話を重ね、欧州や中東を含む国際情勢の激変と東アジアに与えうる影響について認識共有の幅を広げる努力を急ぐべきである。迂遠なようはあるが、この点について認識を共有できるよう働きかけを強めていくことが、韓国で政権交代が起きた場合でも対日政策への影響を最小限にとどめることにつながると考えられる。もし進歩派政権となった場合には歴史認識問題で厳しい対日姿勢を取ることは所与のものと考えるべきであろうが、その影響を他の政策分野に波及させないよう管理すべきである。
3.韓国外交をめぐって
提言
「民主主義体制」が日韓関係の基盤であることを再確認し、関係強化に努める必要がある。政権交代によって進歩政権が登場する可能性が高くなったが、日韓関係の後退を懸念するのではなく、体制共有をもとに協力パートナーシップを強化していくことに尽力すべきである。
背景
憲法裁判所は、非常戒厳の宣言は大統領の権限の範囲内であると主張した大統領側の主張を退け、「軍と警察を動員して国会などの憲法機関を毀損」し、「民主共和国の主権者である国民の信任を重大に裏切った」ことを理由に、尹錫悦大統領を罷免した。
日本では、6月の韓国大統領選挙で与野党の政権交代が起こり、進歩政権が登場した場合、日韓・日米韓協力が後退しかねないと懸念する声がある。しかし、韓国では戒厳令が常に権威主義的な統治につながってきたことを踏まえると、尹錫悦政権が存続しても韓国の民主主義体制が安定的に続く保障はなかった。
1998年の小渕・金大中共同宣言が高く評価されたのは、その基盤が民主主義という体制共有の中で行われたからである。韓国が民主主義体制を失うことは、日本の国益にはならない。民主主義体制を土台に日韓協力を進化させることが、日韓関係のみならず、東アジアの安定化のために欠かせない。
対韓政策に関するインプリケーション
最有力大統領候補である李在明代表(共に民主党)は、政権を担当することになることを踏まえてなのか、これまでの発言とイメージとは異なる立場を表している。2024年12月26日、水嶋光一駐韓日本大使と面会し、国際関係が複雑化していく中で自由民主陣営の結束が重要であるとし、日米韓・日韓協力関係の重要性を強調した。また、2025年1月30日付『エコノミスト』誌とのインタビューにおいても、李代表は実用主義外交を重視する立場から、「日本との関係をさらに深化させ、韓米日3国の協力を持続していく」という意志を表明した。日本の国防力強化についても「韓日関係が敵対的でないため、韓国に脅威にならない」との見解を述べた。尹政権の外交・安全保障政策との連続性を示したことは、注目すべき点である。進歩勢力が政権をとることで日韓関係が後退してしまうというステレオタイプ的な考えにとらわれることなく、民主主義体制の回復・強化に努める政治勢力との協力を重視し、どのような関係を構築していくべきかを構想すべきである。
4.韓国経済と経済安全保障
提言
従来進めてきた経済安全保障面での対話や協力を、韓国で政権交代があった場合でも引き続き推進する必要がある。さらに、トランプ政権の関税など対外経済政策への対応についても、日韓が十分に意思疎通を図って、場合によっては共同で対処することも検討するべきである。
背景
米中の経済対立と技術覇権競争が激しくなるなかで、日本と韓国は経済安全保障面で協力を進めてきた。特にサプライチェーンの強靱化については、日韓二国間だけでなく日米韓やIPEFの枠組みでも早期警戒システムの立ち上げなど協力関係を強化してきた。日本と韓国は地政学的・地経学的位置が似通っており、韓国は経済安全保障政策を策定するにあたっても日本の政策を多く参照してきた。今後も国際環境の厳しさはさらに強まることが予想されるなかで、日韓が協力をさら強化する余地は大きいであろう。日韓の状況が似通っている点は、トランプ政権の関税政策についても同様である(対米貿易赤字、輸出製品としての自動車の重要性、相互関税の税率等)。基本的にはアメリカと日韓がそれぞれ二国間交渉での解決が優先されるとしても、情報の共有や場合によっては欧州やASEANなども含めた共同対応などは検討可能であろう。韓国の政権が交代した場合の対外政策について現時点で予測するのは難しいが、少なくとも対外経済政策・経済協力の分野で大きく変化することは考えにくい。
対韓政策に関するインプリケーション
経済安全保障分野での具体的な協力は、日韓ともに民間企業主導の経済であるために、サプライチェーン面での国際協力を推進するとしても、直接的管理につながるような政策まで進めることは難しい。それ以外に第三国での資源の共同開発や、将来戦略的に重要になる分野での政府系研究機関間での共同研究開発などに韓国側の関心は高く、日本としても積極的に考慮するべきであろう。
5.韓国社会への視角
提言
韓国の若年層を意識したパブリック・ディプロマシーを強化し、両国民が共鳴できる共通軸を増やしていくことは日韓関係の安定に大きく資する。両国間の往来が劇的に増える中、時代の変化に即した交流プログラムの開発が求められる。視察中心の旧来の訪日プログラムを刷新し、日本独自の取り組みや同世代間での対話・協働を発信する内容へとシフトしていく時期にきている。
背景
日韓国交正常化60周年を迎え、新たな日韓関係の構築を図る上で、世代交代を見据えた人的交流の重要性が一段と増している。両国ともに既成世代とは異なる認識や経験を持つ新たな世代がさまざまな活躍の場で台頭しており、次世代を中心とした市民レベルでの信頼構築が肝要となっている。日韓双方で文学やドラマ、音楽、マンガといったマスカルチャーを通じて発信するメッセージが、互いに幅広い共感を得ている。こうした分野では共同製作やアライアンスなど両国民が連携して形成した成果物が大きなボリュームとなっている。文化を媒介とした相互理解の蓄積は、日韓の大きなアセットとなりつつある。一方、政治指導者の交代によって対日政策や対韓政策が転換しうる現状下では、両国関係にきしみが生じる危うさが拭えない。政治環境の変化によるマイナス作用を退けるためには、きしみを凌駕しうる確固とした共感を土台とし、共通の課題解決を目指す対話と協働を日韓関係の主軸として打ち立てる必要がある。
対韓政策に関するインプリケーション
未来志向の日韓関係を考えるとき、日本と韓国それぞれが直面するのは少子高齢化の進展に伴う人口構造の激変である。両国ともに成長や豊かさ、安定を追求した局面が転換し、衰退と不安にさいなまれる時代を迎えることが想定される。従来あった「日韓の眼差しの不均衡」が是正される一方、ともに社会構造の根本的な変化を迎えるなかで、両国民は共通する課題解決に取り組む同伴者になりうる。未知の課題にどう向き合っていくのか、その解決策を見出し実行するのは日韓の未来世代である。
同じ社会課題に手を携えることから得られる共感や相互信頼は、政治環境の変化にも耐えうる。共感と相互信頼のボリュームゾーンを広げることで、その耐性はさらに強まるだろう。
(2025年4月7日校了)